養育費を受け取るために相手の財産情報を取得する方法:シングルマザー必見<財産開示の方法と注意点>
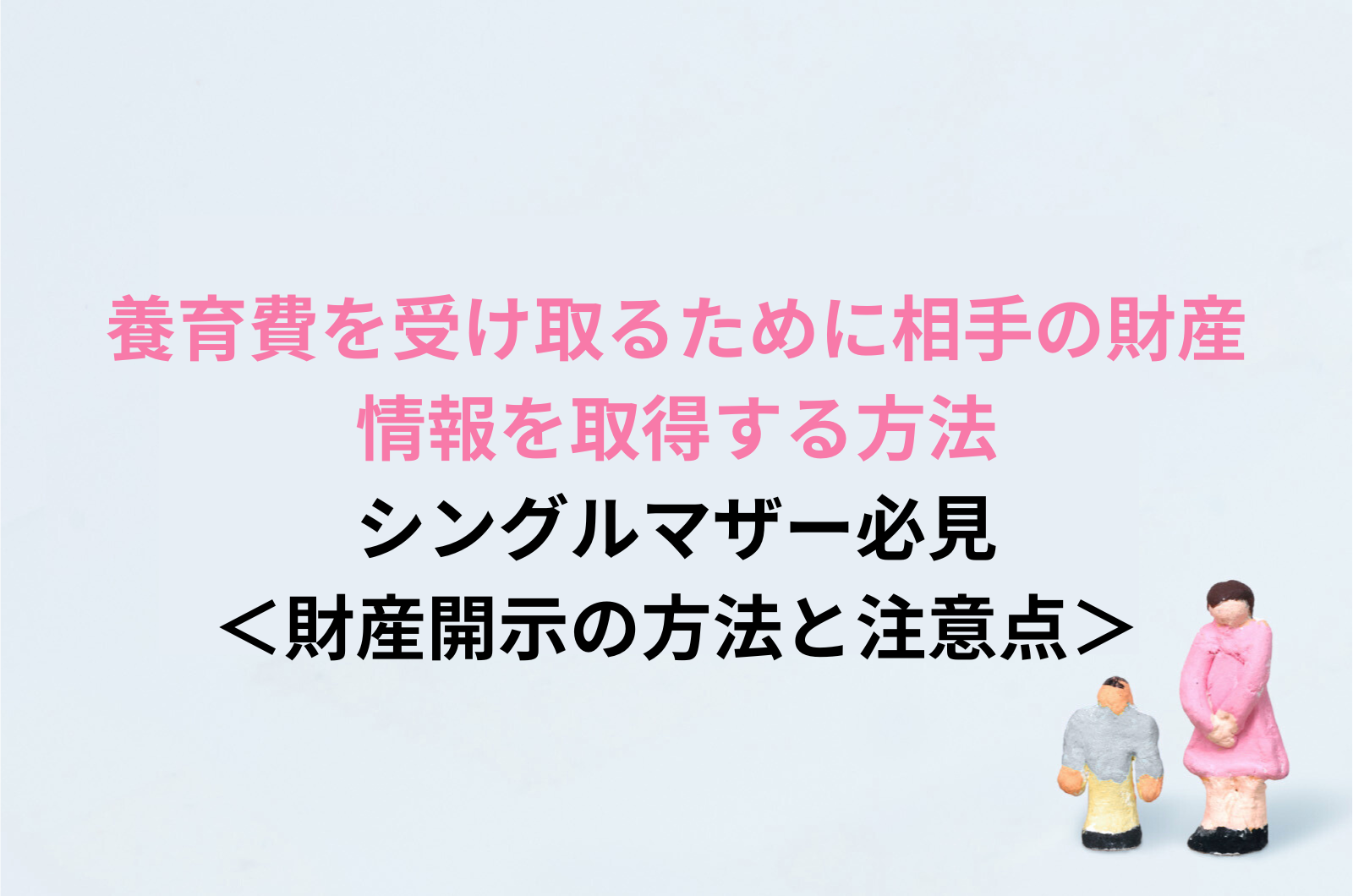
養育費はお子様の成長のための大切な費用です。それにもかかわらず、養育費が支払われないケースは少なくありません。
そのような場合、親として子どもを守るためには、相手の財産を差し押えて回収に充てることを検討することが必要な場合もあります。ただ、そのような場面でも「どうやって相手の財産や勤務先を調べればいいの?」と悩む方も少なくありません。
ここでは、差押えによって養育費を受け取るために重要な役割を果たす「財産開示手続」について、分かりやすく解説します。
目次
財産開示手続とは?
財産開示手続とは、申立人(=養育費を受け取る側)が裁判所に申立てを行い、適法と認められれば裁判所が債務者(=養育費を払う側)を所定の期日に呼び出すことができ、そこで「どんな財産を持っているか」を明らかにさせる制度です。預貯金や勤務先情報(給与の額等)、不動産、自動車、株式など、差押えの対象となる財産が開示されます。
申立人は、ここで開示された情報を基に養育費の回収に向けてどの財産を差し押さえるのが効果的かを検討することとなります。
財産開示手続の流れ
財産開示手続の実施には「債務名義」が必要です。債務名義とは、養育費の支払い義務が明記された正式な書類です。具体的には公証役場で作成する公正証書(執行認諾文言の記載があるもの)や家庭裁判所で行われる家事調停によって作成される調停調書、調停が成立しなかった場合に裁判所が判断を下す審判調書などがあります。(債務名義については総論編で詳しくご紹介しています)。
子どものための費用である養育費の回収へ向けて財産を調査する目的があるとはいえ、財産開示手続は相手を強制的に裁判所に出頭させる強力な手続きですので、当事者間で作成した合意書や覚書では進めることはできません。上記のような法的効力のある債務名義を取得してはじめて実施が可能となります。
債務名義を基に申立書を作成し、債務者の住所地を管轄する地方裁判所へ提出します。この際、収入印紙代や郵便切手代などを裁判所に納める必要があります。
また、申立書面には当事者である申立人と債務者の氏名・住所を記載するとともに以下の財産開示手続特有の要件を満たす必要があります。
【財産開示の要件】
要件1:実施の必要性
財産開示手続は債務者のプライバシーや営業上の秘密に属する財産状況の開示を強制するものですので、以下のA又はBいずれかの要件を満たさなければなりません。
A.強制執行(又は担保権実行)における配当等の手続(申立日より6か月以上前に終了したものを除く)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかったこと
(例:実際に債務者の財産を差し押さえたものの、配当等の手続きにおいて未払い養育費の一部しか回収ができなかった場合)
B.知れている財産に対する強制執行(又は担保権実行)を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済が得られないことの疎明があったこと
(例:申立人側で把握している債務者名義の預貯金口座からは未払い養育費全額の回収見込みがない場合)
なお、上記Bの要件の場合、財産開示手続申立書とともに財産調査結果報告書という、申立人が知っている財産がどれだけ存在するのか,そしてそれらの財産に対する強制執行を実施しても,請求債権の完全な弁済を得られないことを示す書面の提出が求められます。
要件2:申立日前3年以内に、債務者が財産開示期日においてその財産について陳述をしていないこと
養育費を払わない債務者といえども、プライバシー保護の見地から、一度、財産開示に応じた債務者は、その時点から3年以内は開示に応じる義務を負わないこととなっています。
要件3:執行障害
債務者が破産等の倒産手続が開始し、それが終了していない場合には財産開示手続の申立てをすることができません。
申立書の提出を受けた裁判所は、上記のような要件を満たしているかを職権で審理・判断し、適法(=債務者を裁判所に呼び出して持っている財産を明らかにさせる必要がある)と認めた場合には財産開示実施決定を発することとなります。
財産開示は相手の財産を調べるための有効な手段である一方、相手の財産権の制限を伴う非常に強力な手続きでもあるため、法的には厳格なルールが定められており、慎重な対応が求められるのです。
裁判所は財産開示期日を決めた後、債務者に実施決定正本とともに期日呼出状と財産目録の提出を促す通知を送付します。
これらの書面を受け取った債務者は告知された期日を迎える前に、自身の財産状況について詳細を記載した財産目録を提出しなければなりません。
なお、この実施期日は通常、債務者側の都合に関係なく、裁判所によって設定されます。
開示期日当日に裁判所に出頭した債務者は自分の財産状況について陳述します。申立人側も期日に出席して質問をすることが可能ですが、都合がつかない場合には質問事項を記載した書面を事前に提出して、当日欠席しても裁判所から債務者に対して質問してもらうこともできます。ただ、質問内容は、差し押さえることで未払い養育費の回収に充てられそうな財産の調査に必要な範囲に限定されますので、財産開示に直接関係のない質問はできません。
また、これまで養育費の支払いから逃れようとしていた相手方ではあれば、期日当日に正当な理由なく出頭しなかったり、嘘の申告をしたりする可能性も否めません。このような場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されることもあります。
財産開示の手続きを実施したのみでは差押えの効果は発生しませんので、開示された情報を基に、別途管轄の裁判所に対して種類に応じた財産の差押えの申立てをすることになります。
財産開示の特徴と注意点
財産開示がうまくいかなくても諦めるのはまだ早い?第三者からの情報取得手続とは?
財産開示手続を実施したにも関わらず十分な情報が得られなくても、「第三者からの情報取得手続」を利用してさらなる財産調査が可能な場合もあります。こちらは銀行や市区町村、年金機構、証券会社などの第三者から、相手の銀行口座や勤務先、不動産等の情報を、裁判所を通じて取得する制度です。(情報取得手続きについては情報取得編で詳しくご紹介しています)
まとめ
財産開示手続の申立て自体で直接相手の財産を差し押さえられるわけではない
ただ、財産開示手続を利用することで、相手の財産情報を把握し、その後に差押えによる回収も可能に
相手を所定の期日に強制的に呼び出して財産を開示させる非常に強力な手続き
→それゆえ法律上も特有の要件が存在
・既に知っている財産があればまずはそこから回収することが最優先
・プライバシー保護の観点から原則3年以内に再度の財産開示はできない
・債務者が破産手続き中の場合、終了まで財産開示手続はできない
→ケースによっては裁判所から財産調査結果報告書など様々な書類の提出を求められる
債務者が「正当な理由なく」財産開示期日に出頭しない、あるいは、虚偽の申告をしたような場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性
財産開示とは別の制度として、「第三者からの情報取得手続き」という制度が存在
→財産開示で相手の財産が判明しなかった場合でも銀行や市区町村等から、銀行口座や勤務先等の情報を取得可能
「相手の財産を差し押さえて養育費を回収したいけど、どんな財産を持っているか分からない」という方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください
養育費が払ってもらえない場合に、差押えは未払いの養育費を確実に回収するための非常に有効かつ強力な法的手段です。しかし、実際に差押えを実行するためには、対象となる財産を把握していないと申し立てることができません。こうした場面で大変役立つのが財産開示手続です。
ただ、財産開示を申し立てるには債務名義の取得や申立書の作成など、専門的な知識と正確な手続きが求められます。
そのためご自身で対応しようとすると、制度の複雑さや相手方の対応によって、思うように進められないケースも少なくありません。
弁護士にご相談いただければ、状況に応じた適切な対応方法をご提案し、手続きの代理や必要書類の作成も含めて一貫したサポートを受けることが可能です。
大切なお子さまの生活を守るためにも、まずは一人で抱え込まず、法律の専門家にご相談されることをおすすめいたします。



