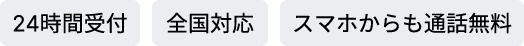同業者による“嫌がらせ予約”を疑ったら?調査・証明・法的対応の流れ

予約を受けたにもかかわらず、当日になって連絡もなく無断キャンセルされた──しかも不審な点が多く、もしかすると近隣の同業者による“嫌がらせ予約”ではないかと疑念を抱いたことはありませんか?
故意にキャンセルを繰り返すことで営業妨害を目的とする行為は、たとえ匿名で行われていたとしても法的に責任を問える可能性があります。本記事では、嫌がらせ予約が疑われる場合の初動対応から、調査・証明・法的措置に至るまでの流れを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
1. まずは「客観的な証拠」を集める
嫌がらせかどうかを判断するためには、以下のような状況や記録が有力な手がかりになります。
- 特定の時間帯・同一日・同一名義で複数予約が入っている
- 架空の電話番号や不自然なメールアドレスで登録されている
- 過去にも同様のキャンセルが短期間に何度も発生している
予約台帳や受付画面のスクリーンショット、通話履歴、メール・LINEのやりとりなどを記録として保存しておきましょう。できれば、ログイン時のIPアドレスなどもシステム側で取得・保管できる設定にしておくと、後々の証明に役立ちます。
2. 状況によっては警察や弁護士に相談を
被害が継続的または組織的と見られる場合は、早めに専門家への相談を検討すべきです。営業妨害や偽計業務妨害といった刑事事件に該当する可能性もあるため、警察への相談も選択肢となります。
また、民事上の損害賠償請求を検討する際には、被害額の算定や加害者の特定が必要となります。そのためにも、弁護士を通じた発信者情報開示請求などの手続きが有効です。
3. 法的措置の前にできる「現実的対策」
すぐに訴訟などに踏み切らなくとも、以下のような現場レベルの対応で被害の抑止が可能です。
- 予約時に電話番号認証やクレジットカード情報の入力を求める
- 明らかに怪しい予約には確認電話をかける
- 不審アカウントの再予約を自動的にブロックするシステム設定
被害が続くようであれば、こうした運用ルールの見直しと、外部の専門家による支援を併用することが重要です。
まとめ|「証拠」と「継続的な記録」が法的対応への第一歩
同業者などによる嫌がらせ予約は、店舗の経営を脅かす深刻な問題です。法的な責任を問うには、感情的な対応ではなく、客観的証拠と冷静な記録・対処が不可欠です。
『キャンセル料請求代行navi』では、こうしたケースでもまずは弁護士が事実を整理し、SMSによる穏やかな請求対応をサポートしています。悪質なケースかどうか判断に迷う場合でも、まずはお気軽にご相談ください。実情に即したアドバイスをご提供いたします。