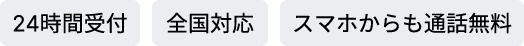弁護士が教える“悪質予約者リスト”の作り方と個人情報の取り扱い注意点

無断キャンセル(いわゆるドタキャン)を繰り返す一部の顧客に対し、店舗として何らかの対策を講じたいと考えるのは当然のことです。 そのひとつとして注目されるのが、「悪質予約者リスト」の作成です。しかし、こうしたリストの作成や運用には個人情報保護法との関係を十分に理解しておく必要があります。 本記事では、店舗が法的に問題なく悪質予約者リストを作成・活用するためのポイントを、弁護士が解説します。
1. 悪質予約者リストは「個人情報」
氏名・電話番号・予約履歴・キャンセルの有無などを記録するリストは、個人を特定できる情報を含むため、個人情報保護法の適用を受けます。
そのため、以下のような点に留意する必要があります:
- リストの利用目的を社内で明確に定める
- 第三者(他店など)への情報提供は原則NG
- 漏えい・不正アクセスを防ぐための管理体制を整える
悪質だからといって自由に共有したり晒したりすることはできず、法的リスクを招く可能性があります。
2. リスト化の判断基準を統一する
「一度のドタキャンで即リスト入り」では不当扱いとされるおそれがあります。
リストに登録する際は、一定の基準(例:無断キャンセルが複数回発生、連絡なし・支払いなし等)を設け、主観でなく事実に基づいた対応を徹底しましょう。
また、記録には以下の情報を簡潔に残すとよいでしょう。
- 予約日時・人数・連絡有無
- キャンセルポリシーの事前説明の有無
- 実際のキャンセル理由(もし確認できていれば)
3. 記録は社内利用のみにとどめる
仮に「この人には次回以降の予約を受けない」という内部ルールを作ることは可能ですが、他店舗と情報を共有する「ブラックリスト」的運用は法律違反になるおそれがあります。
あくまで、自店舗内での予約管理の一環として利用することに留めましょう。必要であれば、顧客に対し「過去のキャンセル履歴を踏まえ、今回はご予約をお断りする場合があります」と丁寧に案内するのが無難です。
まとめ|店舗内での記録・管理は合法、第三者提供はNG
悪質予約者に対する対応は、法的ルールに従いながら慎重に行うことが求められます。
悪意のあるキャンセルへの対応として記録を残すことは問題ありませんが、その取り扱い方を誤ると、逆に顧客から訴えられるリスクもあります。
『キャンセル料請求代行navi』では、記録をもとに弁護士がSMSでの穏当な請求代行を行っており、店舗の法的リスクを最小限にしながら回収をサポートしています。 「この予約履歴、請求に使えるの?」と迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。