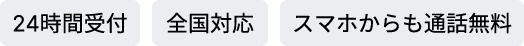キャンセルポリシー未告知でも請求できる?“事前合意なし”のキャンセル料と法的限界
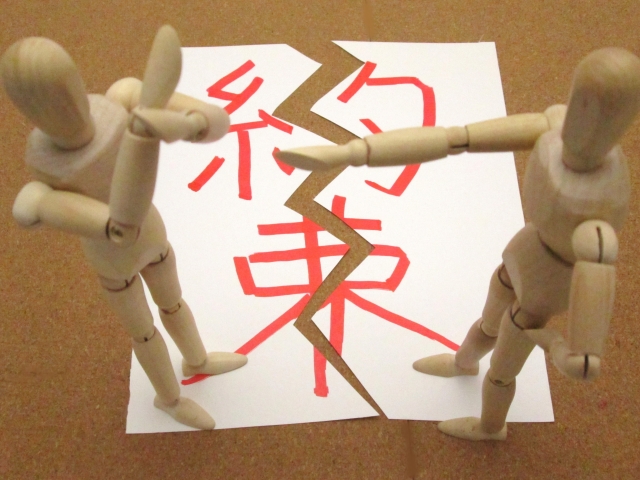
キャンセルが発生した際、キャンセル料を請求したくても「事前に伝えていなかった…」「告知の文言が曖昧だった…」といったケースに悩む店舗も少なくありません。 果たして、キャンセルポリシーの事前合意がないままでも、法的にキャンセル料を請求することはできるのでしょうか?
本記事では、キャンセルポリシー未告知時の請求可否や法的限界について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
1. キャンセル料請求の法的根拠とは?
キャンセル料の請求は、「予約=契約」とみなされることを前提に成立します。
つまり、契約が成立しているにもかかわらず一方的にキャンセルされたことによる損害を、契約違反として請求できるというロジックです。
ただし、契約の内容やキャンセル時の損害額があいまいな場合、法的に「どこまで請求できるか」は限定されます。
2. ポリシー未告知でも「合理的な損害」として一部請求は可能
たとえキャンセルポリシーを明示していなかった場合でも、実際に損害が発生していれば、その損害額については民法上の「損害賠償請求」として請求が可能な場合があります。
たとえば以下のようなケースが該当します:
- 材料や人員を確保していたため費用が発生していた
- 他の予約を断っていたことで機会損失があった
3. 明示していれば「合意」として強い効力が認められる
一方で、事前にキャンセルポリシーを予約ページや電話口などで明示し、かつ同意を得ていた場合には、法的効力が高く認められます。
例えば以下のような対応が望ましいとされます:
- ネット予約時のチェックボックス同意
- 電話予約時の口頭での説明とメモ
- 店頭での書面提示と署名
こうした事前の説明・同意の有無が、実際にトラブルが起きたときの請求可否を大きく左右します。
4. 「言った・言わない」のトラブルを防ぐには?
ポリシーを伝えたつもりでも、後から「聞いていない」と言われるケースもあります。
そのため、以下のような記録の保存が有効です:
- LINEやDMの予約メッセージ履歴
- 電話内容の録音
- 予約台帳へのメモ
これらが残っていれば、キャンセルポリシーの合意があったことの証明に役立ちます。
まとめ|未告知でも一部請求は可能だが、合意があれば圧倒的に有利
キャンセル料の請求は、たとえポリシーを事前に告知していなかった場合でも損害が発生していれば一部可能です。
とはいえ、明示的な合意がある場合に比べ、請求額や対応の妥当性を証明するハードルは格段に高くなります。
『キャンセル料請求代行navi』では、予約内容ややり取りの履歴をもとに、弁護士がSMSで丁寧に請求を代行しています。
「ポリシーを伝えていなかったが、損害は出ている…」とお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。