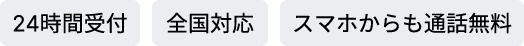キャンセル料請求には“明示的な同意”が必要?注意書きだけで通用するのかを解説

飲食店や美容サロンなどの予約制ビジネスにおいて、無断キャンセルは売上に直接的なダメージを与えます。その対策として「キャンセル料を請求したい」と考える方も多いですが、気になるのが“同意の有無”です。
「予約ページやホームページに注意書きとしてキャンセルポリシーを書いてあるだけで、請求はできるのか?」
この記事では、“明示的な同意”の必要性と、注意文だけでは不十分になり得る理由を、法的観点から分かりやすく解説します。
1. 予約=契約。その中にキャンセルポリシーが含まれるかが争点
キャンセル料を請求する法的根拠は、予約時点で成立する「契約」に基づいています。
問題は、キャンセル料に関するルール(ポリシー)が、その契約内容に明示的に含まれていたかどうか。これは、顧客にとって不利益となる条件(解約時に費用が発生する等)だからこそ、“明示され、かつ同意された”ことが必要とされるのです。
2. 「注意書きに書いてあるだけ」では同意とは言えない場合も
「サイトのフッターに“キャンセル料がかかる場合があります”と書いてある」
「予約確認メールの最後に小さく書いてある」
このような形では、顧客が実際に見ていなかった・認識していなかったという主張が通ってしまうリスクがあります。
特に消費者契約では、顧客に一方的に不利益となる内容は、“周知されており、理解・了承された”ことが法的有効性の条件になります。注意書きがあっても、形式的・視認性が低い場合には「同意があった」とは認められないことも。
3. 明示的同意が成立しやすい伝え方・仕組みとは
紙の同意書は不要ですが、明示的な同意を証明できるような設計は必要です。以下のような方法が実務上有効です。
- オンライン予約時に「キャンセルポリシーに同意する」チェックボックスを設ける
- 口頭予約時に「当日キャンセルは◯%の料金が発生する」と明確に伝える
- 予約確定メール・LINEなどでポリシーを再通知し、記録を残す
これらは「顧客が知った上で予約した」ことを示す間接的な証拠として、実務・裁判上でも有効性が高まります。
4. では「暗黙の同意」はどう扱われる?
店舗によっては、「うちは予約制だから、キャンセル料があるのは当然だと思っていた」といった暗黙的な理解を期待しているケースもあります。
しかし、法律上、黙示の合意(=言わなくても理解されているという合意)は、顧客に不利益を負わせる契約条件の根拠としては不十分とされています。あくまで、顧客が「知らされていた」「了承していた」と明確に主張できる仕組みを整えておく必要があります。
5. 明示的同意がないとどうなる?
キャンセル料を請求しても、相手が「そんな説明は受けていない」と反論した場合、トラブルに発展するリスクが高まります。最悪の場合、少額訴訟やクレーム対応に時間と労力を奪われ、事業に悪影響を及ぼします。
こうした事態を防ぐためにも、キャンセルポリシーの明示と同意取得の仕組みを予約導線に組み込んでおくことが重要です。
まとめ|“注意書き”ではなく“明示的同意”がトラブル回避の鍵
キャンセル料を請求するためには、ただ文言を書いておけば良いというものではなく、お客様に伝わり、理解されたことが明確に示せる状態=明示的同意が必要です。
『キャンセル料請求代行navi』では、弁護士と連携し、店舗の予約フローに沿った“トラブルにならない伝え方・同意の取得方法”の整備もサポートしています。