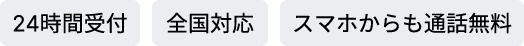客同士の“なりすまし予約”に注意!悪質行為への民事・刑事対応とは?
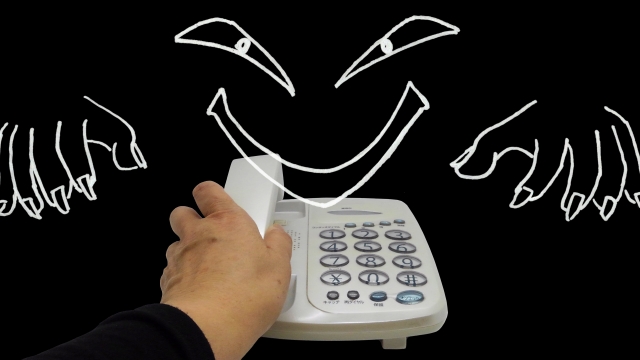
最近、飲食店や美容室などの業界で増えているトラブルのひとつが、「なりすまし予約」です。
例えば、ある顧客が別の顧客の名前を騙って予約を入れることで、その人の信用を落としたり、トラブルに巻き込むことを目的とした悪質なケースが報告されています。
本記事では、なりすまし予約が発生した場合の民事・刑事上の対応方法や、未然に防ぐための対策を弁護士の視点で解説します。
なりすまし予約とは?どのようなケースがある?
「なりすまし予約」とは、他人の名前や連絡先を使用して予約を行う行為を指します。
主なケースとしては以下のようなものが挙げられます:
- 嫌がらせ目的での虚偽予約(予約当日に来店せず、キャンセル料請求だけが発生)
- ライバル関係にある顧客による信用失墜行為
- 元交際相手への嫌がらせとして美容室に虚偽予約
こうした行為は、店舗だけでなく実際に名前を使われた顧客にとっても reputational damage(信用毀損)につながります。
民事上の責任:損害賠償請求は可能?
なりすまし予約が原因で店舗に実際の損害(人件費・材料費・逸失利益など)が発生した場合、民事上の損害賠償請求が可能です。
ただし、加害者の特定が前提となるため、まずは下記のような証拠確保が必要です:
- 予約時の電話番号、メールアドレス、LINE IDの記録
- IPアドレスの取得が可能な予約システムの導入
- なりすまされた顧客からの事情聴取・証言
これらをもとに、弁護士を通じた発信者情報開示請求などを検討することになります。
刑事罰の可能性:偽計業務妨害罪に該当するか?
なりすまし予約は、刑法第233条の「偽計業務妨害罪」に該当する可能性があります。
実際に予約が成立し、店舗が通常営業に支障を来した場合、「偽計(虚偽情報)により他人の業務を妨害した」と評価され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
警察への被害届提出や、証拠提出が必要ですが、実際に立件される事例も存在しており、毅然とした対応が求められます。
なりすまし予約を防ぐ店舗側の対策
トラブルを未然に防ぐために、以下のような対策が効果的です。
- 予約時に電話番号認証やSMS確認コードを導入する
- 常連・新規で運用ルールを分ける(新規は事前決済など)
- 顧客情報をもとに、過去の予約履歴を即座に照合できる体制を整える
また、万が一トラブルが発生した場合のために、予約内容を記録・保存しておくことも重要です。
まとめ|悪質行為には民事・刑事両面での対応を
なりすまし予約は単なるイタズラではなく、業務妨害や名誉毀損といった重大な違法行為にあたります。
『キャンセル料請求代行navi』では、加害者の特定から損害賠償請求、警察との連携まで、弁護士が一貫してサポートいたします。
悪質ななりすましにお困りの店舗様は、まずはご相談ください。